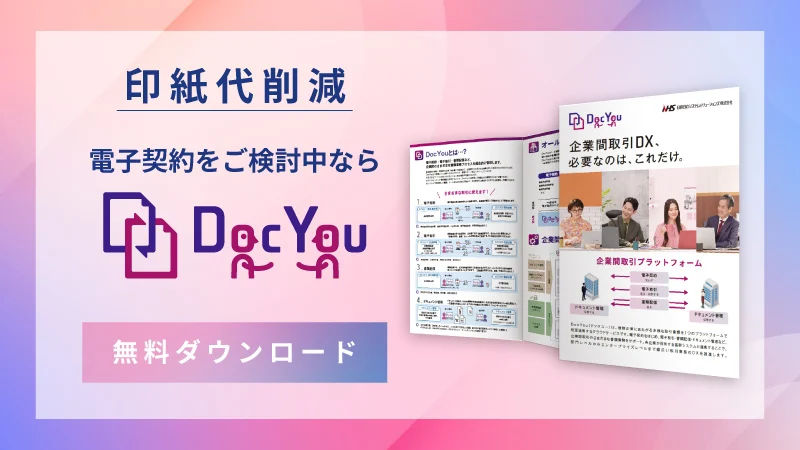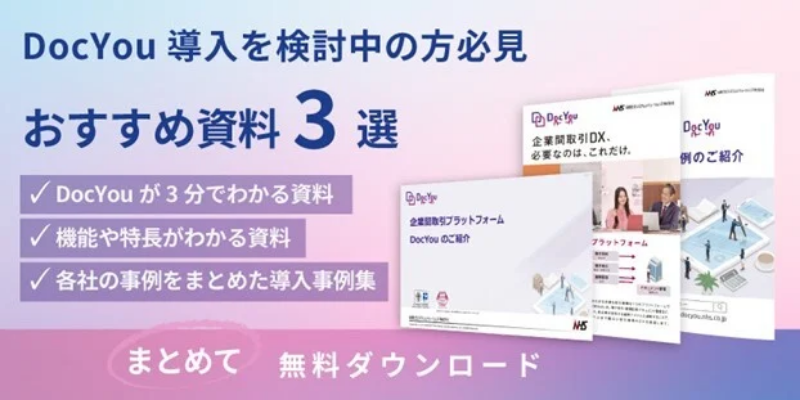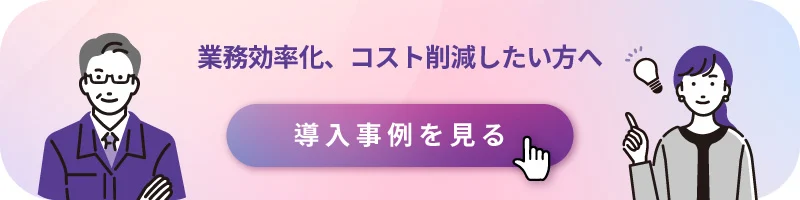「この契約書、収入印紙は必要?」
契約書を作成する際、こんな疑問を持ったことはありませんか?
印紙税法では、契約書などの「課税文書」に収入印紙を貼ることで、印紙税を納める義務が定められています。ただし、すべての契約書が対象というわけではなく、文書の種類や内容によって課税・非課税が分かれます。
さらに近年では、契約書を電子データで締結する「電子契約」の普及により、紙の契約書を作成しないことで印紙税の負担を回避できるケースも増えています。
本記事では、収入印紙が必要な契約書の見分け方や、印紙税の基本的な仕組み、電子契約によるコスト削減のポイントまで、実務に役立つ情報をわかりやすく解説します。
収入印紙とは?仕組みと税法上の役割をやさしく解説
まずは、収入印紙がなぜ必要なのか、その背景や仕組みを理解しておきましょう。
収入印紙とは、国が税金や手数料を徴収するために発行している証票で、印紙税法により定められた「課税文書」に貼付することで納税が完了する仕組みです。税務署への申告や振込などの手続きは不要で、文書に印紙を貼るだけで納税が成立するという手軽さが特徴です。
しかしその反面、貼り忘れや金額の誤りがあると、過怠税(ペナルティ)や追徴課税が課されることも。企業間取引や個人契約を問わず、契約書の種類によっては印紙税の対象となるため、知らずに放置してしまうと後から思わぬ負担が生じる可能性があります。
また、収入印紙は単なる「紙の証票」ではなく、法律に基づいて厳格に運用されている納税手段です。契約書の内容や金額によって税額が変わるため、正確な理解と運用が欠かせません。
さらに、災害時などには印紙税の減免措置が講じられることもあります。こうした特例を活用するには、所定の手続きや条件を満たす必要があるため、制度の概要を把握しておくことも重要です。
まずは、自社の契約書がどのような文書に該当するのかを確認し、印紙税法の基本を押さえておきましょう。
収入印紙とは何か?印紙税法で定められた納税方法
収入印紙は、印紙税法に基づいて発行される納税用の証票です。契約書や領収書など、課税対象となる文書に貼付することで税金を納めたとみなされます。
貼付した印紙には消印(割印)を施す必要があり、これは「使用済み」であることを示すとともに、誰が発行した文書かを明確にする役割も果たします。消印がない場合、納税が完了していないと判断されることがあるため、注意が必要です。
課税文書と非課税文書の違いとは?契約書の見分け方
印紙税法では、契約書の内容や目的によって課税対象かどうかが判断されます。
たとえば、不動産売買契約書や金銭消費貸借契約書などは典型的な課税文書です。一方で、雇用契約書や物品販売契約書などは非課税文書に分類されるため、収入印紙の貼付は不要です。
契約書の形式だけでなく、契約の目的や記載内容も課税判断のポイントとなるため、文書の中身をしっかり確認することが大切です。
以下の一覧表では、代表的な契約書の種類ごとに「課税文書」か「非課税文書」かを分類し、印紙税の要否をわかりやすく整理しています。契約書作成や確認の際の参考にしてください。

詳しい情報や文書ごとの判断基準については、国税庁ホームページをご確認ください。
国税庁ホームページ「課税文書に該当するかの判断」
領収書や証明書など他の文書との混同に注意
契約書と領収書、証明書などはそれぞれ異なる課税区分に属します。
たとえば、領収書は5万円以上の金額が記載されている場合に印紙税が課されますが、契約そのものを証する文書ではないため、契約書とは別の区分で検討が必要です。
また、覚書や確認書などが契約の効力を持つと判断される場合、課税対象となる可能性もあるため、文書の目的と内容を明確にすることが重要です。
収入印紙が必要になる主な契約書の種類

印紙税法では、契約書などの文書を「号数」によって分類し、それぞれに課税の有無や税額が定められています。収入印紙が必要かどうかは、契約書の名称ではなく内容や法的効力によって判断されるため、正確な理解が不可欠です。
ここでは、代表的な課税文書の種類と、それぞれに該当する契約書の具体例を紹介します。契約金額によって税額が大きく変動するケースもあるため、契約書作成時には慎重な確認が求められます。
第1号文書:不動産売買契約書・金銭消費貸借契約書など
不動産売買契約書や金銭消費貸借契約書は、契約金額が大きくなる傾向があり、印紙税額も高額になることが多い文書です。
不動産売買契約書の場合は物件の売買金額、金銭消費貸借契約書では借入額に応じて、納税額が変動します。
たとえば、令和7年現在の税率では、不動産売買契約書において契約金額が500万円を超え1,000万円以下の場合は1万円の印紙税が課されます。
契約金額ごとの印紙税額の詳細は、国税庁ホームページにて最新情報をご確認ください。国税庁ホームページ「印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで」
第2号文書:工事請負契約書・業務請負契約書など
建設工事や業務委託など、成果物の完成を目的とする契約は第2号文書に分類されます。契約金額に応じて、200円から最大60万円まで税額が変動します。
清掃や警備などの無形サービスを含む場合もあり、請負契約の対象や金額範囲などの契約内容を正確に把握し、適切な印紙を貼付することが重要です。
第5号文書:合併契約書・吸収分割契約書・新設分割契約書
企業再編に関する契約書は第5号文書に該当し、資産や株式、負債の移転内容によって契約金額が大きくなる傾向があります。印紙税額も高額になるため、専門家と相談しながら契約書を作成することが推奨されます。
印紙税額は一律で、1通あたり「4万円」です。
第7号文書:取引基本契約書・業務委託契約書など
継続的な取引関係を定める契約書は、第7号文書に該当し、課税対象となる場合があります(契約期間が3か月以内かつ更新の定めのないものは除く)。
印紙税額は一律で、1通あたり「4,000円」です。ただし、契約金額が明記されている場合は、請負契約書などの第2号文書に該当する可能性があり、印紙税額が契約金額に応じて変動するため注意が必要です。
また、継続的な取引関係を定める取引基本契約書のほか、個別の役務提供を定める業務委託契約書も、内容によっては課税文書となる場合があります。
第12号文書:信託契約書
信託契約書は、財産の管理や運用を第三者に委託する際に作成される文書です。契約内容には、信託財産の種類、信託期間、受益者の指定などが含まれます。専門的な内容が多いため、税理士や法務担当者と連携しながら確認することが重要です。
印紙税額は一律で、1通あたり「200円」です。
第13号文書:保証契約書
保証契約書は、債務者が返済できない場合に保証人が代わりに支払うことを約束する文書で、第13号文書に該当します。
保証契約はリスク管理の観点から重要な契約であり、印紙税の扱いを誤ると後々のトラブルにつながるため、契約書の内容を慎重に確認しましょう。
印紙税額は一律で、1通あたり「200円」です。
第14号文書:寄託契約書(金銭・有価証券)
寄託契約書は、金銭や有価証券などの財産を保管・管理してもらうための契約で、第14号文書に分類されます。単に預けるだけの契約であれば非課税となる場合もありますが、保管料や管理方法などが明記されていると課税対象になることがあります。
契約書の文言によって課税・非課税が判断されるため、曖昧な表現を避け、明確な記載を心がけることが大切です。
印紙税額は一律で、1通あたり「200円」です。
第15号文書:債権譲渡契約書・債務引受契約書
債権譲渡契約書や債務引受契約書は、金融取引や企業間の資金調達において頻繁に利用される文書で、第15号文書に該当します。
これらの契約は金額が大きくなる傾向があるため、印紙税額も高額になる可能性があります。契約書作成時には、金額の記載方法や課税対象の判断を慎重に行いましょう。
印紙税額は、契約金額が1万円未満の場合は非課税、1万円以上または契約金額の記載がない場合は1通あたり「200円」です。
収入印紙が不要な契約書と判断基準

契約書のなかには、課税対象外とされる文書も多く存在します。
契約書の形をとっていても、その性質が労働契約や物品販売契約などに該当する場合は、収入印紙を貼付する必要がありません。どのような契約が非課税なのか、判断基準を把握しておくと、無駄なコストを避けることができます。
商品の販売契約書・不動産賃貸借契約書は非課税
物品販売など、モノを売買する契約は一般に印紙税法では課税対象外とされています。また、不動産の賃貸借契約書も非課税文書に分類され、敷金や礼金などの取り決めが記載されていても印紙税はかかりません。
ただし、賃貸借契約と同時に何らかの有償サービス契約が含まれる場合は、別途課税文書とみなされる可能性があるため、内容の分離が必要です。
雇用契約や派遣契約も課税対象外
労働力の提供を目的とする雇用契約書や派遣契約書は、印紙税法上の課税対象外です。賃金報酬は労働の対価として扱われるため、契約書自体に印紙税は課されません。
ただし、業務委託の要素が含まれる場合は、課税対象となる可能性があるため、契約内容を精査する必要があります。
契約金額別の印紙税額一覧と軽減措置
ここでは、令和7年(2025年)時点の最新税率に基づいた第1号・第2号文書の印紙税額の早見表と、災害時などの軽減措置について紹介します。
第1号・第2号文書の印紙税は契約金額に応じて段階的に設定されており、「1万円未満は非課税」「500万円超から1,000万円以下は1万円」など、細かな金額帯ごとに定められています。請負や不動産売買の金額が大きい場合は納める税額も増加するため、契約書を作成する前に早見表を確認しておくとスムーズです。
また、大規模災害が起きた際には特例措置が設けられることがあり、要件を満たせば一定期間、印紙税の減免が受けられる場合もあります。こうした制度を知っておくことは、被災地での復興事業や緊急対応時に大きな助けとなるでしょう。
契約金額別の印紙税額早見表(令和7年版)
以下の表は、令和7年(2025年)時点の最新税率に基づいた第1号・第2号文書に該当する契約書の印紙税額を、契約金額別に一覧化したものです。実務での参考資料として、ぜひご活用ください。

最新の情報は、国税庁ホームページにてご確認ください。国税庁ホームページ「印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで」
災害時の特例措置や印紙税の減免制度
自然災害や震災などの影響を受けた地域では、印紙税の減免措置が適用される場合があります。たとえば、東日本大震災や令和2年の豪雨災害では、被災証明書の提出により契約書が非課税扱いとなるケースがありました。
また、平成26年4月1日から令和9年3月31日までの間に作成された以下の契約書には、政策的な軽減措置が適用されます。
- 不動産譲渡契約書(住宅購入など)
- 工事請負契約書(建設・リフォームなど)
軽減措置の詳しい内容については、国税庁ホームページの最新情報をご確認ください。
国税庁ホームページ「不動産売買契約書の印紙税の軽減措置」
印紙税のコストを削減する方法
契約書にかかる印紙税は、契約金額や文書の種類によって負担が大きくなることがあります。特に紙ベースの契約では、契約書1通ごとに数百円〜数千円の印紙税が発生するケースも少なくありません。
電子契約の導入で印紙税ゼロに
電子契約は、紙の契約書とは異なり印紙税の課税対象外です。つまり、電子契約を活用することで、印紙税の負担を完全にゼロにすることが可能です。
電子契約サービス「DocYou」を活用すれば、印紙税の負担をゼロにできるだけでなく、業務全体の生産性向上にもつながります。
- 印紙税ゼロでコスト削減
- 契約書の検索・管理がスムーズ
- 契約業務のDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進
紙ベースの契約から電子契約への移行は、単なるコスト削減にとどまらず、企業の業務改革にもつながる重要な一歩です。
「DocYou」で、契約業務をもっとスマートに始めてみませんか?
収入印紙に関するよくある疑問とトラブル対応
収入印紙に関するトラブルは、実務の現場で意外と多く発生しています。印紙の貼り忘れによる追徴課税や、過大な印紙の貼付で還付請求が必要になるケースも。
早めに対処するほど被害や損失を最小限に抑えられるため、万が一のときの対処法を理解しておくことが重要です。
印紙の還付請求:誤って購入・貼付した場合
収入印紙を誤って購入したり、不要な契約書に貼ってしまった場合でも、未使用かつ消印がない状態であれば、所定の手続きを経て還付請求が可能です。
ただし、消印済みの印紙は原則として還付不可となるため、貼付前の確認が重要です。
誤った税額で印紙を貼ったときの修正方法
契約金額の認識違いや記載ミスなどで、印紙税額が不足していた場合は、追加納付が必要です。税務署に相談し、過怠税が課されるかどうかも確認しましょう。
逆に、印紙を貼りすぎてしまった場合は、還付申請が可能です。正しい契約金額を早期に把握し、必要に応じて修正手続きを進めることが大切です。
まとめ|印紙税の理解と契約業務の最適化へ
収入印紙は、契約書の種類や金額に応じて課税の有無や税額が大きく変わる、重要な税負担のひとつです。特に不動産取引や工事請負など高額な契約では、印紙税額が数万円〜数十万円に及ぶこともあるため、事前の確認と正しい運用が欠かせません。
一方で、電子契約の導入によって、印紙税のコストを大幅に削減することも可能です。DocYouのような電子契約サービスを活用すれば、印紙税ゼロの契約締結が実現でき、業務効率化にもつながります。
実際の導入事例から、電子契約の活用イメージをつかみませんか?
電子契約サービス「DocYou」の導入事例ページでは、さまざまな企業がどのように電子契約を導入し、業務効率化やコスト削減を実現しているのかをご紹介しています。 導入をご検討中の方は、ぜひリアルな活用例をご覧ください。
※本記事は2025/8時点の情報です。
まとめ
百貨店DXを通じたメリットと導入方法
百貨店業界での電子取引の導入は、業務効率化とコスト削減を実現するだけでなく、業務フロー全体を最適化し、取引先との信頼関係を強化する鍵となります。紙ベースの契約や取引書類管理に依存していた従来のプロセスから、クラウドを活用した電子取引に移行することで、以下のようなメリットが得られます。
- オペレーション効率化
契約締結や情報共有がリアルタイムで可能になり、プロセス全体が短縮。 - コスト削減
紙や郵送、保管スペースなどのコストが不要に。無駄なやり取りが減り、全体的なコストパフォーマンスが向上。 - 環境への配慮
ペーパーレス化で、森林資源の保護に貢献。CSRの強調で、消費者や取引先から支持を得やすくなる。
電子取引を導入する際は、現状の業務フローの確認、セキュリティ対策、適切なサービス選定が重要です。また、段階的なテスト導入や取引先への説明を徹底することで、スムーズな移行が可能です。
百貨店DXを進めるためには、電子取引の導入が不可欠です。未来の競争力を高める第一歩として、ぜひ電子取引の活用をご検討ください。