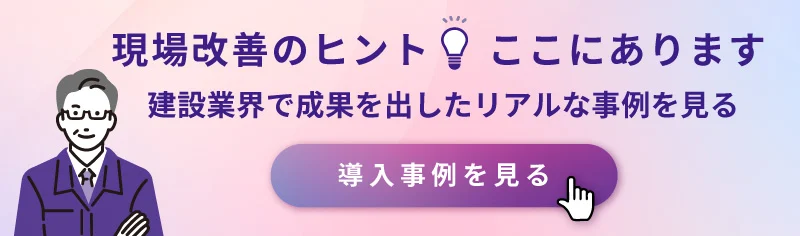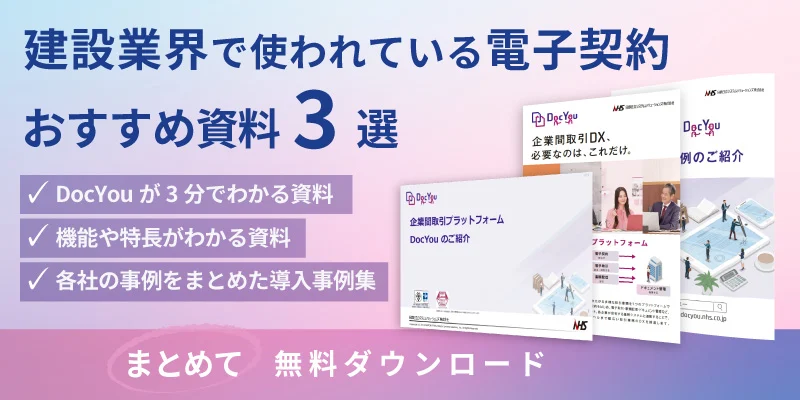建設業界では、デジタル化の流れが急速に進んでいます。その中でも、電子契約は特に注目されている分野です。
これまでの紙ベースの契約は、印刷・押印・郵送といった手間に加え、保管や管理にも多くの時間とコストがかかっていました。こうした課題を解決するために、電子契約を導入する企業が増えています。電子契約サービスを使えば、契約締結までのスピードが大幅にアップし、コスト削減や業務効率化も実現できます。
本記事では、建設業における電子契約の基本知識、法的根拠、導入メリット、実際の事例や導入ステップまでをわかりやすく解説します。これから電子契約を検討する方にとって、役立つ情報が満載です。
電子契約とは?建設業で注目される理由
まずは電子契約の基本的な概要と、建設業界での導入が進む理由を確認しましょう。
電子契約は、契約書を紙ではなく電子データで作成し、オンラインでやり取りして契約を締結する仕組みです。郵送や押印が不要になるため、契約にかかる時間を大幅に短縮できます。さらに、クラウドサービスを使えば、データ保管や本人確認もスムーズに行えます。
こうした利便性やコスト削減効果が、建設業で電子契約が注目される理由です。
特に建設業界は、契約書や関連資料が膨大で、紙の管理に多くのリソースを割いてきました。電子契約を導入すれば、契約情報の共有がスピーディーになり、押印や書類保管の負担も軽減できます。
加えて、法改正や国土交通省によるガイドライン整備が進み、電子契約を導入しやすい環境が整ったことも、普及を後押ししています。
電子契約の定義と仕組み
電子契約は、電子データを正式な契約書として扱う仕組みで、電子署名法などの法律に基づいています。クラウドサービス上に契約書をアップロードし、相手を招待してオンラインで確認・署名するのが一般的な流れです。
電子署名やタイムスタンプを使うことで、改ざん防止や締結日時の証明が可能になり、紙の契約書と同等の法的効力を持ちます。
建設業で導入が進む理由
建設業は、下請企業や資材業者との契約が多く、書類管理が複雑になりやすい業界です。電子契約を導入すれば、契約締結のスピードアップ、工期調整の円滑化、情報共有の効率化が実現します。
さらに、建設業法の改正や国土交通省のガイドライン整備により、電子化の範囲が広がり、導入のハードルは大きく下がりました。今後もデジタル化は進むと予想され、電子契約を早期に導入することが、業界での競争力を維持・強化する鍵となります。
電子契約が広がった背景と建設業法改正の流れ

建設業で電子契約が広がった背景には、法改正や制度整備があります。ここでは、その流れをわかりやすく整理します。
2001年:建設業法改正で電子化がスタート
2001年の建設業法改正により、工事請負契約書を電子データで作成・保管できる仕組みが認められました。それまでは紙の契約書が前提でしたが、この改正をきっかけに、業界全体で電子化の第一歩が踏み出されました。
この時点ではまだ普及は限定的でしたが、書類保管スペースや印刷コストの削減というメリットが注目され、電子化に向けた動きが始まりました。
2018年:クラウド型電子契約サービスの適法性が明確化
2018年には、グレーゾーン解消制度により、国土交通省や経済産業省がクラウド型電子契約サービスの利用に違法性がないことを明確にしました。
これにより、紙での契約が当たり前だった建設業界でも、安心してクラウド型電子契約サービスを導入できる環境が整いました。さらに、クラウド型を利用することで契約情報の共有や検索が格段に容易になる点も、普及を後押しする大きな要因となりました。
2020〜2022年:デジタル改革関連法で普及が加速
2020年から2022年にかけて、デジタル改革関連法が施行され、行政手続きや契約のオンライン化が一気に進みました。
この流れは建設業にも波及し、電子署名の普及や本人確認の強化によって、電子契約の信頼性がさらに高まりました。現在では、工事請負契約や下請契約など、ほとんどの契約書類をオンラインで処理できる環境が整っています。
2025年:働き方改革とICT活用で電子契約の重要性がさらに高まる
2025年の建設業法改正では、労働環境の改善や生産性向上を目的とした施策が強化されました。特に、短工期契約の禁止やICT活用の推進が盛り込まれ、現場の効率化と働き方改革を後押ししています。
この流れにより、電子契約は単なるコスト削減の手段ではなく、ICT活用の一環として重要性がさらに高まっています。契約手続きのオンライン化は、現場と本社、取引先との情報共有をスムーズにし、工期管理や業務効率化に直結します。
今後、電子契約は「導入すれば便利」というレベルを超え、業界全体のデジタル化戦略に欠かせない要素として位置づけられるでしょう。
国土交通省のガイドラインと建設業法における電子契約の要件
建設業で電子契約を導入する際は、国土交通省が定めるガイドラインに沿うことが重要です。特に、契約書の法的有効性を確保するために、次の3つの要件を満たす必要があります。
- 見読性:契約内容を誰でも判読できる状態で保存すること
- 原本性:改ざんを防ぎ、真正性を維持すること
- 本人性:契約当事者を正しく確認できること
これらを満たさない場合、契約が無効になるリスクや行政指導を受ける可能性があります。導入前に、利用する電子契約サービスがこれらの要件をクリアしているかを必ず確認しましょう。
見読性:電子データを判読可能な状態で保存
契約書の電子データは、保存期間中いつでも読める状態を保つ必要があります。PDFなどの標準フォーマットで保存し、PCやタブレット、必要に応じて印刷しても判読できることが求められます。
また、契約情報を容易に検索・抽出できる機能も重要です。
電子契約サービスを選ぶ際は、長期保存やバックアップ体制に加え、機能やインデックス管理が整っているかも確認しましょう。
原本性:改ざん防止と真正性の維持
電子契約では、契約書が作成された時点から改ざんされていないことを証明する仕組みが必要です。電子署名やタイムスタンプを活用することで、誰がいつ署名したかを明確にし、データの信頼性を担保できます。
サービス選定時には、こうした改ざん防止機能が備わっているかを必ず確認しましょう。
本人性:締結当事者の確認と契約の正当性
契約を締結する当事者が本人であることを確認するため、電子署名や認証手段を利用します。ID・パスワードだけでは不十分な場合もあるため、追加認証や公的証明書を組み合わせることが望ましいとされています。
電子契約で扱える建設業の契約書・書類
建設業では、工事請負契約書をはじめ、下請契約書や資材の売買契約書など、幅広い書類が電子契約の対象になります。これらを電子化することで、印紙税や郵送コストの削減、契約締結のスピードアップが可能です。ここでは、代表的な契約書とそのメリットを紹介します。
工事請負契約書と下請契約書
工事請負契約書や下請契約書は、建設業で頻繁に使われる契約書です。従来は紙ベースで印紙税や郵送コストがかかっていましたが、電子契約に切り替えることで印紙税が不要になり、コストを大幅に削減できます。
さらに、クラウド上で契約内容を共有できるため、関係者間の確認作業がスムーズになり、業務効率が向上します。
売買契約書・リース契約書・注文書
資材や機材の売買契約書、リース契約書、注文書も電子契約の対象です。例えば、急な資材発注が必要な場合でも、電子契約ならオンラインで即時対応が可能です。
これにより、工期短縮や在庫リスクの低減が可能になり、現場のスピード感を損なわずに契約を進められます。
建設業で電子契約を導入するメリット
 建設業は契約件数が多く、紙ベースの運用では時間とコストが膨大になります。そのため、電子契約の導入は業務改善に直結する重要な取り組みです。
建設業は契約件数が多く、紙ベースの運用では時間とコストが膨大になります。そのため、電子契約の導入は業務改善に直結する重要な取り組みです。
ここでは、コスト削減・スピードアップ・コンプライアンス強化という3つの視点から、電子契約がもたらす具体的なメリットを解説します。
印紙税・郵送費の削減
紙の契約書では、契約の内容や金額に応じた印紙税が必要です。大量の契約を扱う企業では、この負担は非常に大きくなります。
電子契約に切り替えることで、印紙税が不要になり、郵送費もゼロに。遠方の取引先ともオンラインで契約できるため、コストと時間の両方を削減できます。
契約締結のスピードアップと業務効率化
紙ベースの契約は、署名・押印・郵送・ファイリングといった手間がかかります。電子契約なら、オンラインで署名から契約締結・保管まで完結するため、契約にかかる時間を大幅に短縮できます。
リフォームや資材発注など、スピードが求められる場面で特に効果を発揮します。
コンプライアンス強化とセキュリティの向上
電子契約サービスでは、契約情報がクラウドにデータ保管され、検索や追跡が簡単に行えるようになります。改ざん防止機能や検索性の高さにより、監査や内部統制にも対応しやすくなります。
さらに、複数の現場や遠隔地との取引が増える建設業において、クラウド上で契約データの保護やアクセス権限を集中管理できる点は大きな強みです。これにより、情報漏洩のリスクを減らし、全拠点で統一した安全対策を維持できます。
電子契約導入のステップとポイント
建設業で電子契約を導入する際は、段階的な準備が重要です。対象書類の選定、システム選び、社内ルールの整備まで、計画的に進めることで、スムーズな移行が実現できます。
まず、どの契約書を電子化するかを決め、優先度に応じて導入スケジュールを策定しましょう。次に、法的要件を満たす電子契約サービスを比較検討し、自社の業務フローに最適なシステムを選びます。さらに、取引先への説明と同意取得も重要なステップです。電子契約のメリットや安全性を丁寧に伝えることで、導入後のトラブルを防げます。
最後に、社内でのマニュアル整備や操作研修を実施し、ヘルプデスクやFAQを用意するなど、サポート体制を構築しましょう。こうした準備を徹底することで、導入後に得られる契約手続きの簡素化や業務効率化の効果がより一層高まります。
①対象書類の選定と導入スケジュールの策定
最初に、どの契約書から電子化を始めるかを決めましょう。工事請負契約書など主要な書類を優先し、試験的に導入することで、課題を把握しながら拡大できます。
あわせて、導入スケジュールを策定し関係者と共有することで、社内の混乱を防ぎ、計画的な移行が可能になります。
②電子契約サービスの選定
サービス選定では、法令遵守・セキュリティ・操作性を必ず確認しましょう。クラウド型電子契約サービスなら、バージョンアップやメンテナンスが自動で行われるため、運用負担を軽減できます。自社の業務フローに合ったサービスを選ぶことが、効率化の鍵です。
③取引先への周知
電子契約を導入するには、取引先の同意が欠かせません。セキュリティや法的有効性への不安を解消するため、事前説明を丁寧に行いましょう。導入後のトラブルを防ぐため、承諾書や同意書を事前に用意しておくと安心です。
④運用フローの整備と社内マニュアル作成
電子契約を本格導入する際には、従来の紙ベースのフローをどのように切り替えるかを明確にしておく必要があります。業務担当者向けのマニュアルや研修コンテンツを用意し、操作に慣れるまで、サポート体制をしっかり整えましょう。明確な手続きルールとガイドラインを設定し、関係者全員で共通理解を持つことが重要です。
建設業界における電子契約の事例
電子契約は、建設業界で契約業務の効率化やコスト削減に大きく貢献しています。導入企業では、紙の契約に伴う印紙税や郵送費の削減、契約締結スピードの向上など、さまざまな効果が報告されています。
例えば、電子契約サービスDocYouを導入した企業では、契約書の電子化による業務効率化やコスト削減を実現し、取引先との情報共有もスムーズになっています。
事例の詳細については、以下のページをご覧ください。




 建設業は契約件数が多く、紙ベースの運用では時間とコストが膨大になります。そのため、電子契約の導入は業務改善に直結する重要な取り組みです。
建設業は契約件数が多く、紙ベースの運用では時間とコストが膨大になります。そのため、電子契約の導入は業務改善に直結する重要な取り組みです。