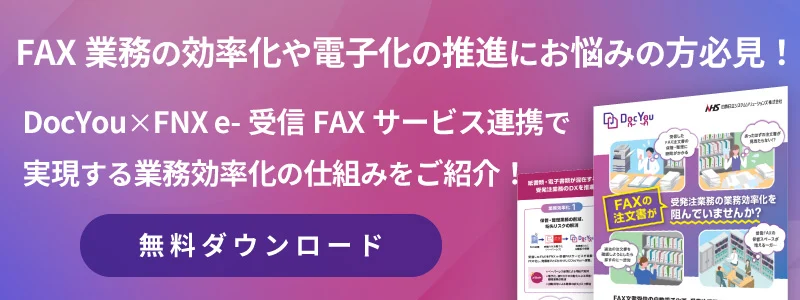製造業・卸売業では、いまだに多くの現場でFAX利用が継続されており、複数取引先との大量帳票のやり取りや管理が負担となっています。また、電子取引が浸透しつつある中で、電子帳簿保存法(以下、電帳法)への対応に苦慮されている企業も少なくありません。
こうした課題解決を支援すべく、株式会社ネクスウェイ(以下、ネクスウェイ)と日鉄日立システムソリューションズ株式会社(以下、日鉄日立システムソリューションズ。インタビュイーの名前部分のみNHS)は、受信したFAXをパソコン上で閲覧や編集、返信が可能になるFAX受信サービス「FNX e-受信FAXサービス」と、電子契約をはじめ、電子取引・書類配信・ドキュメント管理などさまざまな取引業務のDXを推進する企業間取引プラットフォーム「DocYou(ドックユー)」の連携によるソリューションを提供しています。
現場の負担を最小限に抑えつつ、業務革新を実現するその仕組みと、導入効果、そして未来のDX戦略について、両社担当者にインタビューしました。

(左)株式会社ネクスウェイ
ビジネスコミュニケーション事業部
ビジネスコミュニケーショングループ 兼 企画グループ 田口 諒 様
(右)日鉄日立システムソリューションズ株式会社
営業統括本部 ソリューション営業部 シニアマネジャー 神山 俊輔
紙の帳票管理で高まる業務負荷と情報漏えいリスク。それでもデジタルFAXの浸透が進まないワケ

まずは、今回の連携ソリューションが生まれた背景についてお伺いします。製造業・卸売業では、現在もFAXでの受発注業務が根強く残っていると聞きます。お二人は、その背景にどのような事情や課題があると考えていますか。
NHS・神山:最大の要因は商習慣だと考えています。長年のやり方を継続することが前提になっており、急にやり方を変えるのが難しい。加えて、IT導入によるメリットが想像しにくいということがあると感じています。
現在に至るまで、今のやり方で多少の不便さを感じる部分はあれど、「そういうものだ」で基本的には大きな問題もなく業務が回っている。そこにITを活用しましょうとなって、どの程度自分たちの仕事が楽になるのかの具体的なイメージが掴めないため変える必要性を感じにくい、あるいはやり方が変わって、本当に自分たちで運用できるのかという不安もある。その結果、現状維持が選択されがちなのだと思います。
ネクスウェイ・田口様:おっしゃる通りで、商習慣による固定観念の強さは根強いと思います。実際に、「困っていないのに、なぜ変えるのか」という声を現場で聞くこともあります。
NHS・神山:さらに、紙ならではのメリットがあるのも事実です。例えばFAXで注文書が届いた瞬間に、紙を見ながら棚卸しやピッキング作業ができる。紙そのものがチェックリストになり、納品書や注文書とひとまとめで現場を回せます。もし電子化だけを先行させると、「一度事務所でパソコンを立ち上げ、Web上で確認して、印刷して現場へ持ち込む」というオペレーションになり、かえって非効率になり得ます。ここは現場の動線や環境に依存する論点ですよね。

ネクスウェイ・田口様:それから、実はFAXが「届いた時の音」の役割も大きな役割を果たしています。もちろん設定にもよるとは思いますが、パソコンのメールだと受信時に音が鳴らず、かつフォルダの中で埋もれてしまうことも多々あります。それによって重要な連絡を見落としてしまうケースも少なくないと言います。その点、FAXは電話のコール音もそうですが、印字された紙が物理的に出てくるものなので、どうしても音が出ます。それによって確認漏れや書類の放置を防ぐ効果があると聞きます。加えて、一人一台のパソコンが用意されていない企業や現場もまだまだ多く、紙なら使い回しが効くという即時性や利便性が支持されている部分もあります。
NHS・神山:ITリテラシーは個人の能力に依存する課題だと捉えがちですが、実際は環境要因も大きいのですよね。現場や部署単位でパソコンを共用し、共通メールアドレスで対応しているケースは、製造業・卸売業に限らず他業界にも見られます。
ネクスウェイ・田口様:その一方で、複数取引先との大量帳票によって、業務負荷がかかっているという現実があります。特にFAX・メールなど複数チャネルでのやり取りが増えるほど業務負荷は増大し、情報漏えいリスクも高まります。データは各所に散在し、電帳法への対応の観点でも管理が複雑化する。慣れや使い勝手の良さと、ガバナンスや効率化への対応。このトレードオフが、お客様の大きな悩みになっていると感じています。
「FAX番号変更なしでデジタル化」「電帳法に対応した形式で書類を一元管理」現場に優しい2つのサービスとは

今お話しいただいた状況・課題への対応として、ネクスウェイの「FNX e-受信FAXサービス」と日鉄日立システムソリューションズの「DocYou」を連携したソリューションを提供しています。具体的な内容を教えていただけますか。
ネクスウェイ・田口様:まずサービスの概要からお話しすると、ネクスウェイの「FNX e-受信FAXサービス」は、受信したFAXを仕分け・閲覧・検索・編集・返信までWeb上で完結できるサービスです。FAX回線に専用アダプタを取り付けるだけでデジタル化できるので基幹システムの改修は不要、かつ現在のFAX番号を変更せずに導入できます。これにより、書類の紛失や保管場所の確保といった紙運用の課題を解消し、FAX業務の電子化と効率化を両立できます。
NHS・神山:当社の「DocYou」は、複数企業にまたがる多様な取引書類を1つのプラットフォームで相互連携できるクラウドサービスです。電子契約、電子取引、書類配信、ドキュメント管理など企業間取引の書類業務全般をサポートし、各社の基幹システムとも連携して部門から全社レベルまでDXを推進します。

今回の連携では、FAXで受信した注文書・納品書などの帳票をFNX e-受信FAXサービスで電子化・仕分けし、そのデータをDocYouへ連携。あらかじめDocYou上に登録済みの請求書・契約書データとも一元化でき、電帳法における電子取引の保存要件を満たした形式で保存・管理が可能になります。
現場の課題に対し、それぞれのサービスの特徴がどのように対応しているのでしょうか。
NHS・神山:私の視点から申し上げると、FNX e-受信FAXサービスの強みは「入口の徹底的な簡素化」だと感じています。回線とFAX機の間にアダプタを挟むだけで自動的にPDF化し、紙を残さない運用に切り替えられる。その導入の手軽さは大きな特徴ではないでしょうか。
さらに、PDF化して終わりではありません。発信元の番号や帳票の属性などを加味して自動仕分け・メタ情報付与・保管まで対応しています。従来は「紙で受領→スキャン→ファイルサーバーに格納→手作業で仕分け」という手間がかかっていましたが、その一連の業務を効率化できる。定量的な評価が難しい領域ながら、実務では確実な効率化につながると見ています。
ネクスウェイ・田口様:ありがとうございます。多くのお客様から当サービスを評価していただいている点が、「番号を変えなくてよいこと」です。FAX電子化のサービスは以前から存在しますが、番号変更が前提のものが多く、取引先への周知や発注機会損失のリスクが導入のボトルネックになっていました。そこで、私たちのサービスは既存の番号のまま電子化できるように設計しています。
加えて、使い勝手にもこだわっています。電子化は推進しつつも、現場の方がこれまでどおりの感覚でパソコンの画面上で操作できるUIにしています。急にやり方が変わって業務が回らなくなることのないよう、現場にできる限り負担をかけないように工夫しています。
NHS・神山:「量」も重要なポイントだと思っています。月に数件のFAXであれば情報漏えいリスクや業務負荷は見えにくいのですが、毎日100枚〜1,000枚規模で受信する現場では、運用や管理の負担が急速に膨らみます。ここで電子化・自動仕分け・保管の価値が一気に顕在化しますよね。
さらに多拠点運用におけるメリットも大きいです。例えば、本社が東京にある企業で、大阪や福岡などの各拠点で紙を個別管理していると、原本の取り扱いや郵送などで手間やコスト、時間的なロスが生じがちです。FNX e-受信FAXサービスなら、どの拠点で受けたFAXも同一基盤へ集約し、同じポリシーで管理できます。
ネクスウェイ・田口様:それに伴い、拠点間フォローがしやすくなるのも導入効果の一つです。例えば事務担当の方が急にお休みや在宅勤務になったときでも、他拠点やリモート環境からアクセスして対応できます。結果的に、業務の属人化を抑え、長く安心して働きやすい職場環境の構築によって離職リスクの低減にもつながると考えています。
NHS・神山:DocYouの特徴は、電帳法やインボイス制度への対応に活用でき、取引先ごとの使い分けが不要で、送受信した書類を組織全体で一元管理できる点にあります。電子契約はもちろん、見積依頼・見積回答、注文・注文請書など各種書類の双方向送受信、請求書の一括配信までカバー。企業間取引の標準業務を広く支える基盤としてご活用いただいています。
デジタルFAXのその先にある、電帳法への対応や保管・運用まで一気に効率化!

なぜ今回、協業という形で連携することになったのでしょうか。
NHS・神山:まず冒頭申し上げたように、これまで同様「業務を回していく」というだけであれば、紙で受け取ったFAXをそのまま原本保管する運用でも問題はありません。しかし日々100〜1,000件単位でFAXが届く現場では、そもそもすべてのFAXに目を通し、内容に応じてオフィス内の所定の位置に保管するという作業だけでも相当な時間が必要ですし、「あのファイルはどこにあるのか」「誰がいつ登録したか」などの確認も大きな手間となります。その上でさらに、電帳法における区分の一つである「スキャナ保存」の対応をするとなれば、受領後のスキャン、タイムスタンプ付与、さらに取引年月・金額・相手先などで検索可能にするなどの運用設計も必要となってくるため、その負担は計り知れません。
そうした状況に対し今回のソリューションでは、ネクスウェイさんの「FNX e-受信 FAXサービス」によってFAX受信の時点でPDF化(電子化)、発信番号や帳票属性も踏まえた自動仕分けまで行った状態でDocYouへ保存されるので、分類と保存、そして後々の検索の課題にもすべて対応可能です。
一つ留意しておくべきことといえば、受信されたFAXが電子化される時点で「電子取引」となるため、2024年1月以降原則義務化*1であり、「電子取引のデータ保存」となるため、原本保管の頃とは保存要件が変わることを、運用的には意識をする必要があるということでしょうか。
*1:システム対応が困難であるなど、やむを得ない事情がある場合に限り、所轄税務署長への申請と承認を得ることで、電子取引データの保存義務の適用が猶予されるケースもある。ただし、この猶予措置の適用を受けている場合でも、税務調査の際には保存された電子データをダウンロードの求めに応じ、提示できるようにしておく必要がある。
ネクスウェイさんの立場から、DocYou連携の意義をどう見ていますか。
ネクスウェイ・田口様:電子取引としての保存要件の意識といっても、DocYouへのデータの引き渡しで対応できているので安心ですね。電帳法における文書の保存期間は、法人の場合、帳簿や取引書類には原則7年、最長10年となっています。各社の保管方法はまちまちで、お客様側での対応になるため当社ではカバーできない領域でした。そこに対して、「FNX e-受信FAXサービス」で電子化し、DocYouで保存という流れにすることで、電帳法に対応した形式で保管・運用まで含めて効率化していくことができます。そこに連携の大きな意義を感じています。

NHS・神山:入口側であるFAXの電子化・自動仕分け・効率化はネクスウェイさんの強みで、お客様の課題のど真ん中を解決します。加えてDocYouは、デジタル化されたその先で、データを適正に保存・統合管理する役割。「電子化はできた。でも電帳法としてどう管理すれば」というお悩みに対して、DocYouが受け皿になります。結果としてお客様は、チャネルや書類種別ごとの細かなルールを意識せずに、一気通貫で要件を満たせるようになります。
今回の連携はFAX起点ですが、例えばメールで届くPDFはそのままアップロードできますし、郵送された紙はスキャナ保存の要件に沿ってスキャン・保管が可能です。チャネル横断で同一ポリシーのもと管理することができます。
協業の決め手になったポイントを教えてください。
NHS・神山:DocYouは保管だけでなく発信(電子契約や書類配信)もできますが、受領側、特にFAXで受領した書類の扱いは、当社単独では完全なシステム化が難しい領域でした。そこの課題を埋めてくれるのがネクスウェイさんでした。
ネクスウェイ・田口様:私自身、以前から交通広告などでDocYouのサービスを見かけることが多く、世の中の認知が進んでいるサービスだと感じていました。そのように認知と信頼のあるサービスとの連携は当社にとって心強く、それが協業を後押しした要因の一つです。
電帳法への対応や“IT化の2周目の課題”に応え、高度なDX推進を見据えた“はじめの一歩”になる

連携ソリューションが導入企業にもたらす効果・メリットについて教えてください。
ネクスウェイ・田口様:当社のFNX e-受信FAXサービスをサービス単体で利用した場合、保管期限内にお客様側でPDFをダウンロードいただくなど、どうしても意識的な運用が必要になります。今回のDocYou連携では、現場の既存フローの中で受領→保存を自動化する仕組みを提供できるようになることが大きなメリットです。お客様が特別な操作や期限管理を強く意識しなくても、普段の業務の延長で適切な保管まで自動的に完了する。結果として、業務ストレスや運用負荷を増やさずに、電帳法を前提とした業務を遂行できます。
NHS・神山:先ほども申し上げたように、紙の商習慣や固定観念はまだ根強く残っています。だからこそ今回の連携のような、業務を大きく変えずに始められる小さな一歩を提供することが重要だと考えています。「意外と大丈夫」という成功体験を積み重ねていただくことで、当初改善を予定していた業務だけでなく、その周辺の領域までIT化を進めるきっかけにつながります。現場の抵抗感を最小限に抑えながらDXを推進する初手として、私たちのソリューションは最適だと思います。
ネクスウェイ・田口様:当社としても、「入口の電子化」でスモールスタートしていただく発想を重視しています。いきなり基幹システムを大改修するのではなく、リスクの小さいところから確実に効率化する。そこから全社的なDX推進へとつないでいくことが大切です。当社が所属するTISインテックグループは業務コンサルから各種ITソリューションまで幅広い選択肢を提供しているので、必要に応じてお客様のあらゆるお悩みを解決できると考えています。
NHS・神山:ここ数年、電帳法の改正をきっかけに、まずは突貫的に対応した企業が多かった印象があります。いまは2周目の課題に突入し、業務効率化と適正な保管を同時に高い水準で実現したい、という次の要求レベルに移行しています。今回の連携によって、電帳法への対応を前提としつつ、業務の断絶をなくしてシームレスにつながる仕組みを提供できると考えています。
現場のITスキル向上を支援し、共創の精神で製造業・卸売業の競争力強化に貢献したい

今回の連携ソリューションは、製造業・卸売業のDX推進にどのような影響を与えるとお考えですか。未来のビジョンや、力を入れていきたい市場戦略についてお聞かせください。
NHS・神山:理想を言えば、FNX e-受信FAXサービスで受けた帳票をその場で電子化し、DocYouで電帳法に対応した形で適正保管した上で、さらにRPA/OCRや各種連携を活用して基幹システムへの自動登録までつなげる、基幹システム全体で一気通貫の流れを実現したいですね。ここまで進むと、現場はさまざまな入力作業から解放され、より本質的な付加価値業務へシフトできます。
こうしたことを実現するには、私たちだけでなくIT企業同士が垣根を越えて共創することが不可欠です。各社の得意領域を掛け合わせ、業界全体を巻き込むプラットフォームとして提供していく。最終的にお客様はもちろん、関係者すべてが恩恵を受ける未来を目指します。
ネクスウェイ・田口様:実は、売上高1,000億円規模や従業員数数千人規模の企業でも、FAX運用は現役だったりします。そのため中小企業はもちろん、準大企業〜大企業まで広く価値を提供できる余地があります。企業の大きさにかかわらず、また製造業・卸売業の垣根も超えて、サプライチェーン全体の変革に貢献したいと考えています。
今、そのビジョン実現に向けて機能拡充に注力しています。例えば、「FAXを電子化してDocYouに保管できるのは良いですね。ところで、“送り返し”はできるのですか」といったお問い合わせをいただくことが多かったので、自動返信機能を追加しました。受信と同時に「注文を受け付けました」「納品予定日○/○」といったテンプレート返信を自動で返せます。例えば食品業界のように即納が常識の世界では、手書き返信・日付記入といった定型作業を画面上の操作だけで自動化することで、現場の負担を着実に減らすことができます。

NHS・神山:確かに、即納が求められる現場での自動返信は非常に合理的な機能ですね。さらにその先の構想としては、受注を受けた後に基幹システムで生成される請書データをDocYouに戻し、メール配信はもちろん、将来的にはDocYouからFAX送信まで一気通貫で行えると理想的です。現在は受信側の連携が中心ですが、送信(発信)側まで含めて双方向の連携を強化できれば、受ける時も送る時も同じ基盤で完結します。お客様のニーズに対し、オールインワンで応えられる世界を構築していきたいですね。
そして、繰り返しになりますが、今回の連携をきっかけに現場のITスキルの底上げにも寄与したいと考えています。まずは業務を大きく変えずに始められる一歩で抵抗感を下げる。成功体験が積み上がればお客様のITに対する認識が変わり、より高度な上位システムとの連携や業務設計そのものの見直しに進むことができます。ネクスウェイさんもDocYouも、FAX・電帳法という入口から周辺業務へ展開可能な選択肢を持っています。
ソリューションの開発自体は企業単体でもできることだと思いますが、知見のある他社と組んだほうが速くて質が上がるという、その共創の姿勢こそが企業のDX推進を支える鍵になりそうですね。
NHS・神山:その通りです。今回の協業のポイントのところでもお話ししたように、全部を自前で網羅するのではなく、得意分野を持ち寄って、Win-Winの関係で連携していく。競合同士でもタッグを組む時代です。より安く、より速くソリューションを届けられるので、結果として、お客様にとってもよい結果になっていくと思っています。

グローバル化が加速する中、日本の商習慣を深く理解する私たちが手を組んで価値提供していくことに、強い使命感を持っています。共創の精神で製造業・卸売業をはじめとする産業全体の競争力の底上げに貢献していきたいですね。
※本記事は2025/9時点の情報です。
まとめ
- FAX番号そのまま、受信書類の電帳法要件を満たして安全に保存
- 現場負担を最小限に抑えながら業務効率化と情報漏えいリスクの解消を両立。従来の業務フローを大きく変えずにFAX電子化と電帳法への対応を同時実現
- 多拠点運用と業務属人化の解消で組織全体の運用効率向上。どの拠点からもアクセス可能で担当者不在時のフォロー体制も構築
- スモールスタートから始める製造業・卸売業のDX推進基盤。IT抵抗感を軽減しながら段階的に高度なシステム連携へ発展可能
関連コンテンツ
企業間取引DX、必要なのは、これだけ
DocYou(ドックユー)の詳しい説明はこちら
FAX業務のカイゼンを加速するクラウドFAX
FNX e-受信FAXサービスの詳しい説明はこちら